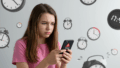2025年8月29日に発表された調査結果によると、20代で「子どもを持ちたい」と考える人の割合が39.7%となり、過去の調査から大幅に減少していることが明らかになりました。これは前回調査から8.4ポイントの減少で、SNSでも「やっぱり将来が不安」「子育てコストが高すぎる」といった声が飛び交っています。
20代が子どもを望まなくなった理由
なぜここまで「子どもを欲しい」と考える若者が減ってしまったのでしょうか。調査では以下のような理由が挙げられています。
- 経済的不安:育児にかかる費用が高すぎる(教育費、医療費、住宅費)。
- キャリアとの両立の難しさ:特に女性を中心に、出産や育児でキャリアが停滞する懸念。
- ライフスタイルの多様化:「結婚や出産は必ずしも人生のゴールではない」という価値観の広がり。
- 将来への不安:年金や社会保障制度への不信感、将来設計の難しさ。
少子化に拍車をかける現状
日本はすでに少子化が深刻化しており、出生数は過去最低を更新し続けています。今回の調査で20代の子どもへの意欲がさらに低下していることは、今後の社会に大きな影響を与える可能性があります。
社会への影響
- 労働人口の減少:若い世代が減ることで、将来的に人手不足がさらに深刻化。
- 経済成長の停滞:消費市場の縮小や社会保障負担の増加。
- 地域コミュニティの弱体化:地方では学校や保育施設の統廃合が進む恐れ。
必要とされる少子化対策
この状況を打破するためには、従来の「子育て支援策」に加えて、より根本的な変革が求められます。
- 経済的支援の強化:出産・育児にかかる費用を実質的に軽減する施策。
- 働き方改革の徹底:育児休業制度や時短勤務を男女ともに利用しやすくする。
- 教育・住宅政策の見直し:学費の負担軽減や、子育て世帯が住みやすい住宅支援。
- 社会の意識改革:「子どもを持たない人生」も尊重しつつ、持ちたい人を積極的に後押しする環境整備。
まとめ:個人の選択と社会の支え合いがカギ
20代の「子どもを持ちたい」意欲の低下は、日本社会にとって大きな課題です。しかしそれは同時に、若者が直面している現実を浮き彫りにした結果とも言えます。
今後は「子どもを持つ・持たない」という個人の選択を尊重しながらも、子どもを持ちたいと考える人が安心して実現できる社会をつくることが求められます。
あなたはどう考えますか?「子育てがしたい」と思える社会をつくるために、どんな取り組みが必要だと思いますか?